この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題1 医学研究の倫理に関する宣言はどれか。
1.ジュネーブ宣言
2.ヘルシンキ宣言
3.リスボン宣言
4.アルマ・アタ宣言
解答2
解説
1.× ジュネーブ宣言とは、1948年に世界医師会で規定された医の倫理に関する規定であり、ヒポクラテスの誓いをもとにしている。守秘義務などが含まれている。
2.〇 正しい。ヘルシンキ宣言は、医学研究の倫理に関する宣言である。
・ヘルシンキ宣言とは、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の基盤となる倫理的原則を示しているものである。ニュルンベルク綱領とは、医学的研究のための被験者の意思と自由を保護するガイドラインである。ニュルンベルク裁判で問題とされた人体実験において遵守されるべき基本原則を定めた倫理綱領である。1947年に提示された、研究目的の医療行為を行うにあたって厳守すべき10項目の基本原則である。後にヘルシンキ宣言として人を対象とする研究の倫理指針につながった。
3.× リスボン宣言とは、1981年にポルトガルのリスボンで採択され、患者の権利に関する宣言である。①良質の医療を受ける権利、②選択の自由の権利、③自己決定の権利、④情報を得る権利、⑤プライバシーを守られる権利、⑥人間としての尊厳を得る権利が規定されている。
4.× アルマ・アタ宣言とは、プライマリヘルスケアに関する宣言である。すべての人に健康を基本的な人権として認め、その達成の過程において住民の主体的な参加や自己決定権を保障する理念である。すべての人にとって健康を基本的な人権として認め、その達成の過程において住民の主体的な参加や自己決定権を保障する理念である。
問題2 我が国の国民医療費に含まれるのはどれか。
1.予防接種の費用
2.健康診断の費用
3.帝王切開の費用
4.入院時室料差額の費用
解答3
解説
「国民医療費」とは、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものである。この費用には、医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等が含まれる。なお、保険診療の対象とならない評価療養(先進医療(高度医療を含む)等)、選定療養(入院時室料差額分、歯科差額分等)及び不妊治療における生殖補助医療などに要した費用は含まない。また、傷病の治療費に限っているため、(1)正常な妊娠・分娩に要する費用、(2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3)固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用も含まない。
(※一部抜粋:「国民医療費の範囲と推計方法の概要」厚生労働省HPより)
1.× 予防接種の費用は、国民医療費に含まれない。なぜなら、傷病の治療費に限っているため。
・予防接種は、病気の重症化を予防するための行為である。
2.× 健康診断の費用は、国民医療費に含まれない。なぜなら、傷病の治療費に限っているため。
・健康診断は、現時点での健康状態を確認したり、病気の早期発見を目指したりするものである。
3.〇 正しい。帝王切開の費用は、我が国の国民医療費に含まれる。なぜなら、帝王切開は、医学的な必要性に基づいて行われる「医療行為(手術)」であるため。したがって、医療保険が適用される費用として、国民医療費の対象となる。
4.× 入院時の質量差額の費用は、国民医療費に含まれない。なぜなら、傷病の治療費に限っているため。
・国民医療費は、保険診療の範囲内で推計される標準的な医療費を対象としている。差額ベッド代は、患者の希望によって標準的な病室よりも設備が整った病室を利用した場合に発生する追加費用である。必須の医療行為そのものにかかる費用ではないため、国民医療費の算出からは除外される。
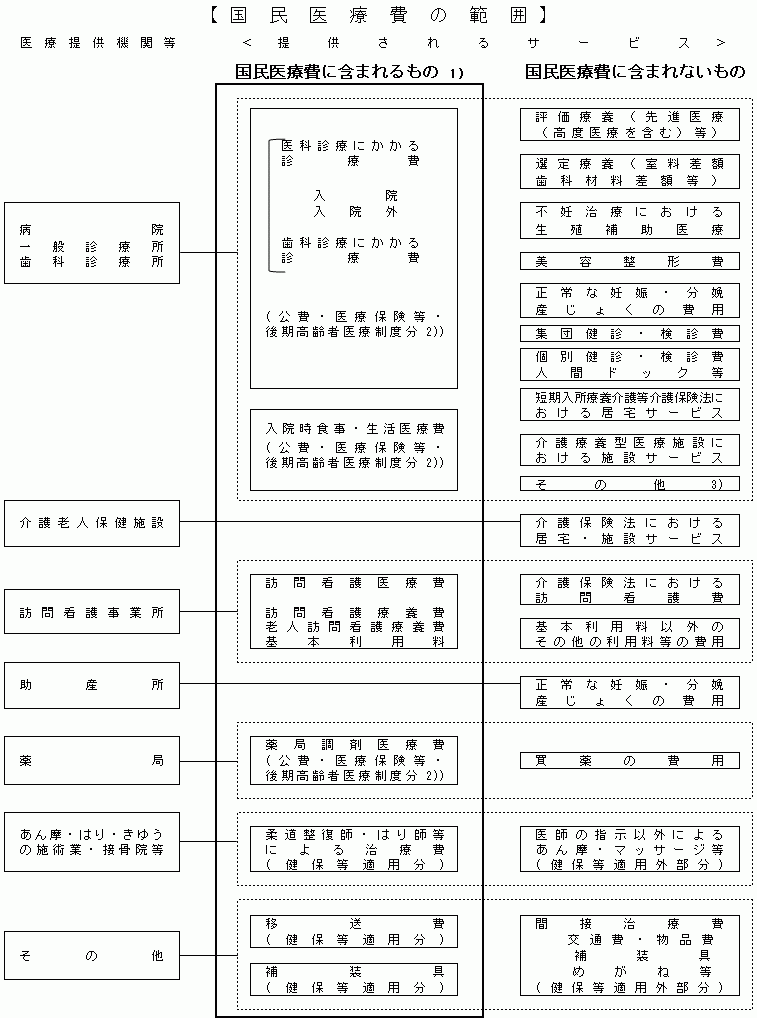 (※図引用:「国民医療費の範囲と推計方法の概要」厚生労働省HPより)
(※図引用:「国民医療費の範囲と推計方法の概要」厚生労働省HPより)
問題3 公費医療の対象とならないのはどれか。
1.生活保護法による医療扶助
2.母子保健法による養育医療
3.労働者災害補償保険法による療養
4.精神保健福祉による措置入院
解答3
解説
公費とは、国家または公共団体の費用のことをさす。公費負担医療とは、医療費の全額もしくは大部分を公的管理された基金が負担する医療制度のことである。医療保障制度には、社会保険における医療保険のほかに、公的扶助、社会福祉、公衆衛生等における公費負担医療制度がある。
1.〇 生活保護法による医療扶助は、公費医療の対象である。生活保護制度は、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。被保護人員は約216.4万人(平成27年度,1か月平均)で過去最高となっている。
2.〇 母子保健法による養育医療は、公費医療の対象である。養育医療制度は、母子保健法に基づき、出生時の体重が2,000グラム以下や、特定の症状があり入院養育が必要な未熟児に対し、その医療費を公費で負担する制度である。
・母子保健法とは、母性、乳幼児の健康の保持および増進を目的とした法律である。母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。各種届出は市町村長または特別区、指定都市の区長に届け出る。
3.× 労働者災害補償保険法による療養は、公費医療の対象とならない。なぜなら、労働者災害補償保険(労災保険)は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれているため。
・労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。業務上や通勤途中の事故等による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して必要な保険給付を行う、労働保険制度の一つである。
4.〇 精神保健福祉による措置入院は、公費医療の対象である。なぜなら、措置入院にかかる医療費は、本人の同意なしに行われる公権力の発動として、原則として都道府県や市町村が公費で負担する。
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>は、措置入院を規定する法律である。精神障害者の入院について5つの入院形態(任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院)を定めている。
問題4 パターナリズムに基づいている行為はどれか。
1.治療方針は医療者が決める。
2.個人情報の保護に取り組む。
3.患者の自己決定権を尊重する。
4.患者が医療内容の説明を受ける。
解答1
解説
パターナリズムとは、父権主義ともいい、弱い立場の者の意思・判断に関係なく強い立場の者が介入・干渉し、それに従うべきだとする考えのことである。医療において、患者の意思にかかわらず、医師などの専門家に任せた治療を進めることを指す。
1.〇 正しい。治療方針は、「医療者」が決める。この行為は、まさにパターナリズムに基づいている。医療者が患者の意見を聞かず、あるいは患者の希望を無視して、医療者自身の専門知識や経験に基づき「患者にとって最善である」と判断した治療方針を一方的に決定することは、パターナリズムの典型的な例である。これは、患者の自律性や自己決定権を十分に尊重していない態度といえる。
2.× 個人情報の保護に取り組む。
・個人情報の保護は、患者のプライバシー権や秘密保持の権利を尊重することに基づいている。
3.× 患者の自己決定権を尊重する。
・自己決定権とは、一定の個人的な事柄について、公権力から干渉されることなく、自由に決定する権利である。 例えば、結婚・出産・治療・服装・髪型・趣味など、家族生活・医療・ライフスタイル等に関する選択、決定について、公共の福祉に反しない限りにおいて尊重される。
4.× 患者が医療内容の説明を受ける。
・これは、インフォームド・コンセントに基づいている。インフォームド・コンセントは、「十分な説明を受けたうえでの同意・承諾」を意味する。医療者側から診断結果を伝え、治療法の選択肢を提示し、予想される予後などについて説明したうえで、患者自らが治療方針を選択し、同意のもとで医療を行うことを指す。診断結果の伝達には「癌の告知」という重要な問題も含まれる。
問題5 疾病予防に関するハイリスクアプローチでないのはどれか。
1.喫煙者に禁煙指導の実施
2.市民を対象としたウォーキング大会の実施
3.糖尿病予備軍に運動指導の実施
4.塩分摂取量が多い者に食事指導の実施
解答2
解説
・ポピュラーアプローチ(ポピュレーションストラテジー):対象を限定せず地域や職場など、集団全体に働きかけてリスクを下げる方法である。一次予防とされる。
・ハイリスクアプローチ(ハイリスクストラテジー):リスクの高いものに対象を絞り込んで働きかける方法である。2次予防とされる。
1.〇 正しい。喫煙者に禁煙指導の実施は、ハイリスクアプローチである。なぜなら、「喫煙者」という対象を絞り込んでいるため。ちなみに、喫煙者は、肺がん、心疾患、脳卒中など、様々な病気にかかるリスクが非喫煙者よりも著しく高い集団である。
2.× 市民を対象としたウォーキング大会の実施は、ハイリスクアプローチでない。これは、ポピュラーアプローチに該当する。なぜなら、「市民全体」という特定の病気のリスクに限定されない幅広い集団を対象としているため。つまり、高リスク者だけでなく、誰でも参加できるような形(予防的な活動も含め)で実施されている。
3.〇 正しい。糖尿病予備軍に運動指導の実施は、ハイリスクアプローチである。なぜなら、「糖尿病予備軍」という対象を絞り込んでいるため。ちなみに、糖尿病予備軍とは、血糖値が正常よりも高いものの、まだ糖尿病と診断される基準には達していない状態である。したがって、将来的に糖尿病を発症するリスクが高い集団といえる。
4.〇 正しい。塩分摂取量が多い者に食事指導の実施は、ハイリスクアプローチである。なぜなら、「塩分摂取量が多い者」という対象を絞り込んでいるため。ちなみに、塩分の過剰摂取は、高血圧やそれに起因する脳卒中や心疾患などのリスクを高める。
 国試オタク
国試オタク 

