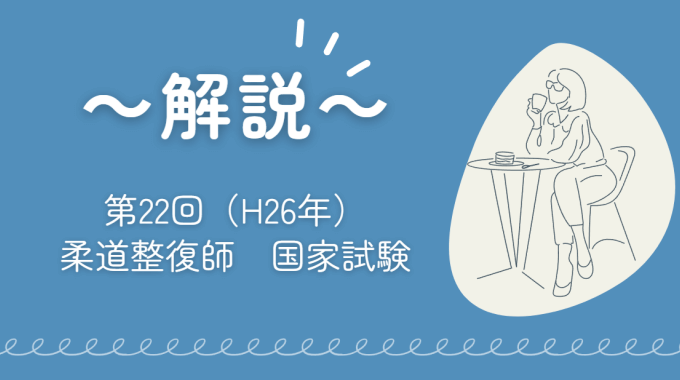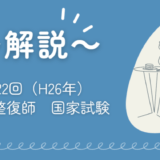この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題21.骨折における外固定の目的で適切でないのはどれか。
1.疼痛の軽減
2.炎症の鎮静化
3.整復位の保持
4.リモデリング期の短縮
解答4
解説
内固定法とは、鋼線やネジなどの金属で骨折した部分を体の中で直接固定する方法のこと。
外固定法とは、ギプス包帯法やギプス副子法、装具療法で固定する方法のこと。
1.〇 疼痛の軽減は、骨折における外固定の目的である。なぜなら、骨折部の異常可動を防ぐことで痛みの原因を減らすことができるため。
2.〇 炎症の鎮静化は、骨折における外固定の目的である。なぜなら、患部の安静を保てるため。
3.〇 整復位の保持は、骨折における外固定の目的である。なぜなら、再転位の予防に寄与するため。
4.× リモデリング期の短縮は、骨折における外固定の目的で適切でない。なぜなら、外固定は、主に初期の炎症期・仮骨形成期における安定化を目的としているため。
骨折の治癒過程において、「①炎症期→②仮骨形成期→③仮骨硬化期→④リモデリング期」となる。
①炎症期:骨折後2〜3日で活動のピークを迎える。骨折した人が経験する初期の痛みのほとんどがこの炎症によるものである。
②仮骨形成期:骨折後1週間が過ぎると骨芽細胞が活動し、1週間目から14週目ぐらいは仮骨が形成する時期である。仮骨とは、骨折した場合に折れたり欠損したりした骨の代わりに、新たにできる不完全な骨組織のことである。
③仮骨硬化期:8週間目から36週間目ぐらいにあたる。
④リモデリング期:硬化仮骨が患部の機能とともに回復に、本体の骨に吸収、添加作用していく時期である。これが20週目から52週目ぐらいにあたる。
問題22.オーバーラッピングフィンガーの主な要因はどれか。
1.側方転位
2.屈曲転位
3.捻転転位
4.延長転位
解答3
解説
1.× 側方転位とは、骨折によって分断された骨が側方に平行移動したものをいう。
2.× 屈曲転位とは、傾くように曲がって角度がついたものをいう。屈曲転位は通常、伸展や反対方向への力を用いた他の整復方法で治療される。
3.〇 正しい。捻転転位は、オーバーラッピングフィンガーの主な要因である。
・捻転転位とは、ねじれるように軸回転したものをいう。
・オーバーラッピングフィンガーとは、手の中手骨・基節骨を骨折した際に回旋転位(捻転転位)を残してしまった時に見られる変形治癒のことをいう。指の骨折が原因で指が重なる変形が残ってしまう状態である。
4.× 延長転位とは、離れるように動いたものをいう。
転位とは、骨折などで骨片が本来の位置からずれた状態にあることをいう。骨転位ともいう。骨折時の衝撃で起こる転位を一次性転位と呼び、骨折後の運搬時などの力で起こる転位を二次性転位と呼ぶ。転位は、形状によっても分類される。完全骨折の場合、一カ所の骨折でも複数種類の転位が見られることが多い。転位の見られる骨折の治療では、整復によって骨を本来の位置に戻してから固定する必要がある。
①側方転位とは、骨折によって分断された骨が側方に平行移動したものをいう。
②屈曲転位とは、傾くように曲がって角度がついたものをいう。
③捻転転位とは、ねじれるように軸回転したものをいう。
④延長転位とは、離れるように動いたものをいう。
⑤短縮転位とは、すれ違うように移動し重なったものをいう。
問題23.脱臼の合併症で誤っているのはどれか。
1.関節包の拘縮は関節運動障害の原因となる。
2.陳旧性脱臼は仮性関節窩を形成する。
3.反復性脱臼は関節軟骨損傷を伴う。
4.長期の固定は骨化性筋炎の原因となる。
解答4
解説
1.〇 正しい。関節包の拘縮は、関節運動障害の原因となる。なぜなら、脱臼による炎症や出血が関節包の線維化・癒着を引き起こし、関節の可動性を失わせるため。
・関節包とは、骨と骨があたる部分にはやわらかな軟骨があり、そのまわりは丈夫な袋のことをいう。関節包の内面は、滑膜でおおわれ、滑膜から潤滑油のように滑らかな液が分泌されて、関節の滑りをよくしている。
2.〇 正しい。陳旧性脱臼は、仮性関節窩を形成する。なぜなら、脱臼した骨頭が本来の関節窩に戻らず、周囲組織の反応によって新しい安定位置(偽の関節窩)が形成されるため。
・関節窩とは、関節を構成する、くぼんだ部分のことである。
・陳旧性脱臼とは、関節がはずれた状態が長い間もとに戻らず、そのまま固まってしまったものである。普通の脱臼はすぐに治すが、時間がたつと周りの筋肉や靭帯が固まり、骨が動かしにくくなる。
3.〇 正しい。反復性脱臼は、関節軟骨損傷を伴う。なぜなら、脱臼を繰り返す過程で関節包や靭帯、関節唇、軟骨などが繰り返し損傷し、関節の安定性が失われるため。
・関節軟骨損傷とは、関節軟骨がすり減ったり、裂けたりする状態である。血流が少ないため一度損傷すると自然治癒しにくい特徴がある。進行すると痛みや腫れ、関節の動かしにくさを引き起こし、放置すると変形性関節症につながることもある。
・反復性脱臼とは、一度大きなけがをして関節が脱臼し、その後脱臼を繰り返してしまうものを指す。肩関節、顎関節、膝蓋骨などに発生しやすい。習慣性脱臼や随意性脱臼、反復性脱臼などは病的脱臼に含まれない。反復性脱臼の主な原因は、上腕骨骨頭の骨欠損、関節包の弛緩、一部の関節唇の剥離によって、正常な構造が破綻することである。
4.× 長期の固定は、骨化性筋炎の原因「とはいいにくい」。なぜなら、骨化性筋炎の原因は、筋肉損傷後の出血や過度な刺激であるため。むしろ、長期固定では起こりにくい。
・骨化性筋炎とは、打撲などの外傷によって、筋肉の中に骨と同じような組織ができてしまう疾患のことである。外傷性骨化性筋炎、骨化性筋炎とも言う。 損傷を受けた筋肉が出血して血腫ができたところに、カルシウムが沈着し、石灰化しておこる。大腿部前面に強い打撲を受けた後によくみられる。
問題24.肋骨の単発骨折で正しいのはどれか。
1.浮遊肋骨に好発する。
2.転位は軽度なことが多い。
3.安静時痛が著明である。
4.絆創膏固定は皮膚障害を防止できる。
解答2
解説
1.× 浮遊肋骨(第11~12肋骨)には「起きにくい」。なぜなら、浮遊肋骨は、可動性が大きく、外力を受けても分散しやすいため。したがって、単発骨折は、固定性が高く外力が集中しやすい第5〜9肋骨に好発しやすい。
2.〇 正しい。転位は軽度なことが多い。なぜなら、肋骨は、肋間筋や外肋間膜、胸膜などにより強固に支持されているため。したがって、骨片の移動が制限される。
3.× 「安静時痛」ではなく「呼吸や運動時痛」が著明である。なぜなら、呼吸運動による胸郭の拡張・収縮が、骨折部を刺激するため。したがって、安静時は、骨折部の動きがほとんどないため痛みは比較的軽い。
4.× 絆創膏固定は皮膚障害を防止「するものではない」。むしろ、長期間の使用により皮膚トラブルの原因になりやすい。
・肋骨骨折の屋根瓦状絆創膏固定とは、絆創膏を貼付する範囲をアルコール綿で消毒し、呼気時に貼付していく。その際、乳頭部はガーゼで保護し、肋骨弓下縁から上方に向かって少しずつ重ねながら貼付していく。
問題25.顎関節前方脱臼で正しいのはどれか。
1.高齢男性に多い。
2.直達外力によるものが多い。
3.関節包内脱臼である。
4.閉口位で弾発性に固定される。
解答3
解説
1.× 「高齢男性」ではなく高齢女性に多い。顎関節前方脱臼の男女比は1:1.6程度とされている。ちなみに、顎関節症も女性のほうが2倍ほど多い。確実な原因はわかっていないが、その要因として、①一般に、女性の方が男性より靭帯が柔らかいこと、②顎関節の適合がしっかりしてないこと、③女性ホルモンとの関わりなどがあげられている。
2.× 「直達外力」ではなく介達外力によるものが多い。顎関節前方脱臼は通常、口を大きく開けたとき(例:あくびや大声を出すとき、外力が加わったとき)に発生する。
3.〇 正しい。関節包内脱臼である。一般的な脱臼は、関節包を破って逸脱(関節包外脱臼)するが、肩関節や顎関節の脱臼の多くでは関節包を破ることなく逸脱(関節包内脱臼)する場合が多い。その結果、再発を繰り返す「反復性脱臼」に進展する例が多い。
・関節包とは、骨と骨があたる部分にはやわらかな軟骨があり、そのまわりは丈夫な袋のことをいう。関節包の内面は、滑膜でおおわれ、滑膜から潤滑油のように滑らかな液が分泌されて、関節の滑りをよくしている。
4.× 「閉口位」ではなく開口位で弾発性に固定される。弾発性固定は、脱臼の固有症状である。弾発性固定とは、脱臼した位置で関節が動かなくなる状態をいう。患部を押しても反発するか、動いてもまた脱臼した位置に戻ろうとする特徴がある。
 国試オタク
国試オタク