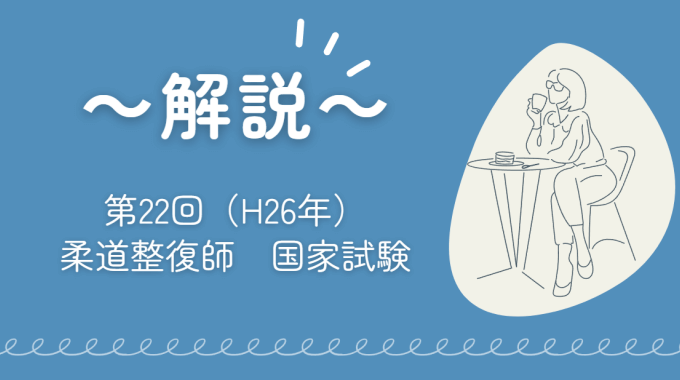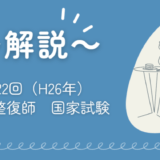この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題26.鎖骨骨折で正しいのはどれか。
1.多くは直達外力で発生する。
2.小児は完全骨折が多い。
3.楔状骨片は成人の骨折でみられる。
4.高齢者では骨壊死を合併しやすい。
解答3
解説
定型的鎖骨骨折は、近位骨片が胸鎖乳突筋の作用で後上方に転移するものをさす。
1.× 多くは「直達外力」ではなく介達外力で発生する。なぜなら、スキーや自転車で転倒して肩や手を地面について骨折するケースが多いため。
・介達外力とは、打撃や圧迫などの外力が加わった部位から離れた部位に体内組織を通じて外力が伝わることである。
2.× 小児は、「完全骨折」ではなく不全骨折(特に若木骨折)が多い。なぜなら、小児の骨が柔軟で、骨折時に骨が折れるよりも曲がる傾向があるため。
3.〇 正しい。楔状骨片は成人の骨折でみられる。なぜなら、成人では鎖骨が硬く脆く、斜め方向の外力により三角形状の骨片(楔状骨片)が形成されやすいため。
・楔状骨片とは、骨折が発生した際に、その名の通り楔形(くさび形)をした骨片のことをいう。この形状は、不規則な力が骨に加わった結果、骨が三つの断片に分かれる骨折、特に螺旋骨折や楔骨折によく見られる。(※読み:けつじょうこっぺん)
4.× 高齢者では骨壊死を合併しやすい「とはいえない」。なぜなら、鎖骨は周囲から豊富な血流を受けているため。
・骨壊死には①症候性(外傷や塞栓症などによる血流途絶が原因)と②特発性(明らかな誘因がない阻血性壊死)がある。血行不良のため骨折後の再生が困難となる。症候性骨壊死が生じやすい部位:①上腕骨解剖頸、②舟状骨、③大腿骨頸部、④大腿骨顆部、⑤距骨である。
問題27.肘内障で誤っているのはどれか。
1.幼小児の発生頻度が高い。
2.手を引っ張られることで発生する。
3.前腕回外位で来所する。
4.整復後は上肢挙上が可能になる。
解答3
解説
肘内障とは、乳幼児に特有の外傷で、橈骨頭が引っ張られることによって、橈骨頭を取り巻いている輪状靭帯と回外筋が橈骨頭からずれた状態(亜脱臼)になったものである。5歳くらいまでの子どもに発症する。 輪状靭帯の付着がしっかりする6歳以降では起こりにくい。
1.〇 正しい。幼小児(1〜5歳)の発生頻度が高い。なぜなら、肘の輪状靭帯がまだ十分に発達しておらず、比較的緩いため。
2.〇 正しい。手を引っ張られることで発生する。なぜなら、受傷機転として、保護者などが子供の手を強く引っ張った際に橈骨頭が亜脱臼することで発生するため。
3.× 前腕「回外位」ではなく回内位で来所する。なぜなら、強い引っ張りによる外力(前腕回内力)が加わり、受傷されるため。多くは、前腕回内位・肘関節軽度屈曲位で来院する。
4.〇 正しい。整復後は上肢挙上が可能になる。なぜなら、整復により橈骨頭が元の位置に戻り、輪状靭帯の挟み込みが解除されるため。
・整復前は、上肢全体を麻痺があるかのようにまったく動かさない。 患肢をだらんと垂らしたまま曲げようとしない、患肢に触れようとすると嫌がり泣き出すといった症状がみられる。
問題28.腱板損傷の検査法はどれか。
1.ドロップアームテスト
2.ヤーガソンテスト
3.スピードテスト
4.サルカスサイン
解答1
解説
1.〇 正しい。ドロップアームテストの陽性は、肩腱板断裂を疑う。方法は、座位で被験者の肩関節を90°より大きく外転させ、検者は手を離す。
2.× ヤーガソンテストの陽性は、上腕二頭筋腱炎を疑う。患者の肘90°屈曲させ、検者は一側の手で肘を固定して、他方の手で患側手首を持つ。次に患者にその前腕を外旋・回外するように指示し、検者はそれに抵抗を加える。
3.× スピードテストは、上腕二頭筋長頭腱の炎症の有無をみる。結節間溝部に痛みがあれば陽性である。
【方法】
被検者:座位で、上肢を下垂・肩関節外旋位から、上肢を前方挙上(肩関節屈曲)してもらう。
検者:肩部と前腕遠位部を把持し、上肢に抵抗をかける。
4.× サルカスサインとは、動揺性肩関節などの肩関節不安定性を評価する検査である。肩関節外転外旋位で、上腕骨頭を後方から前方へ押し出すストレスをかけた際の不安感を確認する。ストレスをかけた際に不安感や怖さを感じたら陽性である。
問題29.大腿骨頸部内側骨折で正しいのはどれか。
1.股関節外転・内旋強制での発生が多い。
2.スカルパ三角部に圧痛を認める。
3.転子果長は短縮する。
4.下肢は内旋位をとる。
解答2
解説
1.× 股関節(過伸展時に)外転・内旋強制での発生が多いのは、「股関節前方脱臼(恥骨上脱臼)」である。
・大腿骨頸部骨折の受傷機転は、主に、高齢者が転倒して衝撃を受けることで、頸部に剪断力が加わることで起きる。
2.〇 正しい。スカルパ三角部に圧痛を認める。なぜなら、スカルパ三角内に大腿骨頸部内側が位置するため。関節包内で生じた炎症や血腫により、この部位に圧痛を感じる。
3.× 転子果長は、「短縮」ではなく左右差はみられない。なぜなら、大腿骨頸部は、転子部より近位であるため。骨折部位が転子果長を跨がないため影響はない。
・転子果長とは、大転子から外果まで距離である。
4.× 下肢は、「内旋位」ではなく外旋位をとる。なぜなら、股関節の外旋筋群のが優位的に牽引するため。また、骨折後に自動運動ができなくなるため、重力により股関節外旋位を取りやすい。
問題30.膝関節損傷と検査法との組合せで適切なのはどれか。
1.半月損傷:グラスピングテスト
2.前十字靭帯損傷:ラックマンテスト
3.後十字靭帯損傷:ワトソン‐ジョーンズテスト
4.内側側副靭帯損傷:マックマレーテスト
解答2
解説
1.× 半月損傷:グラスピングテスト
・グラスピングテストは、腸脛靭帯炎の検査である。やり方は、腸脛靭帯を圧迫してテンションをかけた状態で、膝の曲げ伸ばしで症状が再現されるかどうかで判断する。腸脛靱帯炎の原因は、膝の屈伸運動を繰り返すことによって腸脛靱帯が大腿骨外顆と接触して炎症(滑膜炎)を起こし、疼痛が発生する。 特にマラソンなどの長距離ランナーに好発し、ほかにバスケットボール、水泳、自転車、エアロビクス、バレエ等にも多い。
2.〇 正しい。前十字靭帯損傷:ラックマンテスト
・ラックマンテストは、膝関節前十字靱帯損傷の検査である。背臥位で膝関節を20~30度屈曲させて、下腿部近位端を斜め前方へ引き出す。陽性の場合、脛骨は止まることなく前方に出てくる。
3.× 後十字靭帯損傷:ワトソン‐ジョーンズテスト
・ワトソン・ジョーンズテストは、半月板損傷の検査である。 背臥位になってもらい、右手で踵骨を持ち、左手で膝を固定した状態で、右手で軽くトントンと足を上げる。痛みの誘発で陽性となる。
4.× 内側側副靭帯損傷:マックマレーテスト
・マックマレーテストは、半月板損傷を検査する。①背臥位で膝を完全に屈曲させ片手で踵部を保持する。②下腿を外旋させながら膝を伸展させたときに痛みやクリックを感じれば内側半月の損傷、下腿を内旋させながら膝を伸展させたときに生じるならば外側半月の損傷を示唆する。
 国試オタク
国試オタク