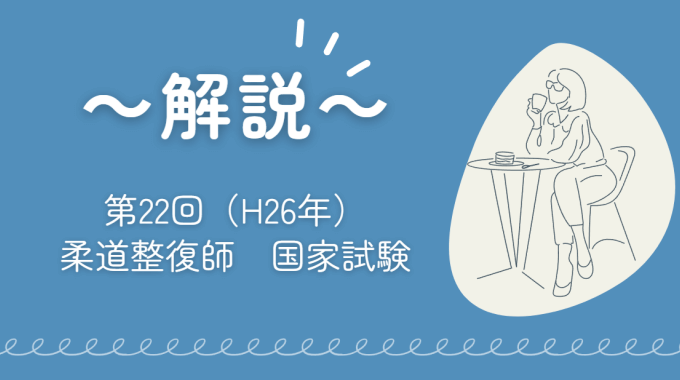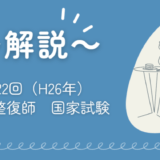この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題16.正しい組合せはどれか。
1.正中神経麻痺:母指対立障害
2.尺骨神経麻痺:下垂手
3.橈骨神経麻痺:猿手変形
4.坐骨神経麻痺:膝伸展不能
解答1
解説
1.〇 正しい。正中神経麻痺:母指対立障害
なぜなら、正中神経は手の母指球筋群を支配しているため。したがって、母指球筋萎縮/猿手/示指のしびれは、正中神経麻痺でみられる。
・正中神経麻痺とは、tear drop sign(ティア ドロップ サイン)または、perfect O(パーフェクト Oテスト)や、Phalen(ファレンテスト)が陽性となる麻痺である。ファーレン徴候(Phalen徴候)とは、手首を曲げて症状の再現性をみる検査である。perfect O(パーフェクト Oテスト)とは、親指と人差し指の先端をくっつけて丸形を作る検査である。
2.× 尺骨神経麻痺は、「下垂手」ではなく鷲手である。
・尺骨神経麻痺とは、尺骨神経損傷により手掌・背の尺側に感覚障害やFroment徴候陽性、鷲手がみられる麻痺である。Froment徴候(フローマン徴候)とは、母指の内転ができなくなり、母指と示指で紙片を保持させると母指が屈曲位をとることである。Guyon管を通るものとして、①尺骨神経、②尺骨動脈である。
3.× 橈骨神経麻痺は、「猿手変形」ではなく下垂手である。
・橈骨神経麻痺とは、母指背側の感覚障害と上腕三頭筋・腕橈骨筋・長、短橈側手根伸筋、総指伸筋などの伸筋群の麻痺(下垂手)を認める。
4.× 坐骨神経麻痺は、膝関節伸展は保たれる。膝関節伸展が不能となるのは、大腿神経麻痺である。なぜなら、膝関節伸展は主に大腿四頭筋が担うため。
・大腿四頭筋の支配神経は、大腿神経(L2~L4)である。大腿四頭筋とは、①大腿直筋、②外側広筋、③中間広筋、④内側広筋の4筋からなる大腿の筋の総称である。
問題17.骨折固有症状の異常可動性はどれか。
1.大きく口を開けると下顎頭が前方に移動するのを触知する。
2.上肢を挙上させると上腕中央部が屈曲するのを触知する。
3.肘に外転力を加えると関節に外反変形が出現する。
4.母指を自分でZ字状に変形させたり元に戻したりできる。
解答2
解説
1.× 大きく口を開けると下顎頭が前方に移動するのを触知する。
これは、正常な顎関節の動きである。
2.〇 正しい。上肢を挙上させると上腕中央部が屈曲するのを触知する。
これは、骨折固有症状の異常可動性の説明である。なぜなら、本来上腕骨は1本の連続した骨体であり、中央部(骨幹部)は関節を介さず動かないため。
3.× 肘に外転力を加えると関節に外反変形が出現する。
これは、肘の内側側副靭帯損傷を示唆する所見である。
・内側側副靭帯とは、肘関節の外側からのストレス(外反ストレス)に抵抗することで、関節の内側部分が開きすぎるのを防ぐ役割を持つ靭帯である。
4.× 母指を自分でZ字状に変形させたり元に戻したりできる。
これは、関節の柔軟性が高いことを意味する。「骨折性異常可動性」ではなく関節性変形である。
・Z状変形とは、手の母指に起こるものであり、IP関節が過伸展している状態のことである。
①弾発性固定:脱臼した位置で関節が動かなくなる状態をいう。患部を押しても反発するか、動いてもまた脱臼した位置に戻ろうとする特徴がある。
②変形:関節が元の位置から逸脱するために、見た目にも変形がみられる。一度脱臼すると、関節の構造が破壊されてしまったり、靭帯や関節包が緩んでしまったりすることで不安定性が残る可能性がある。特に肩関節は、再負傷しやすいといわれている(反復性脱臼)。
問題18.脱臼で正しいのはどれか。
1.外傷性脱臼後に軽微な外力や筋力で脱臼を繰り返すものを習慣性脱臼という。
2.本人の意思で脱臼を起こし、また原位置に復することができるものを反復性脱臼という。
3.大腿骨外顆形成不全に起因する膝蓋骨脱臼は随意性脱臼である。
4.反復性脱臼は肩関節で多くみられる。
解答4
解説
反復性脱臼とは、一度大きなけがをして関節が脱臼し、その後脱臼を繰り返してしまうものを指す。肩関節、顎関節、膝蓋骨などに発生しやすい。習慣性脱臼や随意性脱臼、反復性脱臼などは病的脱臼に含まれない。
反復性脱臼の主な原因は、上腕骨骨頭の骨欠損、関節包の弛緩、一部の関節唇の剥離によって、正常な構造が破綻することである。
1.× 外傷性脱臼後に軽微な外力や筋力で脱臼を繰り返すものを「習慣性脱臼」ではなく反復性脱臼という。なぜなら、「反復性脱臼」は外傷を契機に関節包や靱帯が伸びてしまい、その後軽微な外力や筋収縮でも繰り返し脱臼を起こす状態を指すため。※ただし、反復性脱臼の原因は、あくまでも「一度大きなけが=外傷」である。
2.× 本人の意思で脱臼を起こし、また原位置に復することができるものを「反復性脱臼」ではなく随意性脱臼という。
・随意性脱臼とは、人によっては自らの意思で脱臼させることができる状態である。
3.× 大腿骨外顆形成不全に起因する膝蓋骨脱臼は、随意性脱臼「とはいえない」。
【膝蓋骨脱臼の分類(4つ)】
・外傷性脱臼とは、強い外力により脱臼するもの。
・反復性脱臼とは、初回脱臼後何度も脱臼を繰り返すもの。
・習慣性脱臼とは、同じ姿勢によって毎回脱臼するもの。
・恒常性脱臼とは、姿勢に関係なく常に脱臼しているもの。
4.〇 正しい。反復性脱臼は肩関節で多くみられる。なぜなら、肩関節は可動範囲が広く、関節包や靭帯が緩みやすい構造をしているため。また、一度外傷で関節包や靱帯(特に前下関節包・関節唇)が損傷すると、軽微な外力でも再脱臼を繰り返しやすい特徴を持つ。
問題19.骨折の治癒に好適な条件はどれか。
1.骨折線が関節内にある。
2.骨折部と外界が交通している。
3.両骨折端が血腫内にある。
4.骨折部に絶えず牽引力が作用している。
解答3
解説
・軟部組織の損傷が少ない。
・両骨折端が血腫内にある。
・骨折面の密着した骨折線の長い螺旋状または斜骨折の場合。
・海綿質の骨折、噛合した骨折、若年者、両骨片への血行が良好、細菌感染がない、栄養状態が良好、骨疾患や全身疾患がない、骨折部にかかる力が圧迫力となり剪力が働いていない場合など
1.× 骨折線が関節内にある場合、骨治療の不適な条件である。なぜなら、関節内骨折は関節の動きにより骨片が動きやすいため。また、関節液により骨折部の血腫が洗い流されてしまう。
・関節内骨折とは、骨折が関節の内部にまで及んでいる状態を指す。一方、関節外骨折とは、骨折する際にできる骨折線が関節の内部にない骨折のことである。
2.× 骨折部と外界が交通している場合、骨治療の不適な条件である。なぜなら、開放骨折(骨折部と外界が交通している)は、感染の危険が高いため。
・開放骨折とは、骨折した骨の端が皮膚を突き破って露出したりして、骨折部とつながる傷が皮膚にあるものを指す。この露出により、感染症を生じやすい。
3.〇 正しい。両骨折端が血腫内にあることは、骨折の治癒に好適な条件である。なぜなら、骨折部の血腫は初期の骨癒合過程に重要な役割を果たすため。血腫は細胞の侵入を助け、骨の修復に必要な因子を供給する。
4.× 骨折部に絶えず牽引力が作用している場合、骨治療の不適な条件である。一方、骨折部に働く圧迫力は、骨折の癒合に好適な条件である。なぜなら、圧迫力は骨片の接触面積を増やし、骨癒合に必要な環境を整えるため。したがって、骨折部に適度な圧迫力が働くと、骨片が安定し、骨癒合が促進される。
・骨折端が広く離開している(関節内骨折、開放性骨折)。
・骨折部に絶えず力が作用している。
・骨折部の血腫消失、高度な軟部組織の損傷や欠損、高齢者、細菌感染がある、骨片への血流が悪い、高度の粉砕骨折、栄養状態が不良、骨疾患や全身疾患などがあるなど。
問題20.骨折の整復法で正しいのはどれか。
1.牽引直圧法は最初に捻転転位を除去する。
2.屈曲整復法は筋緊張を増強させて行う。
3.ハンギングキャスト法は牽引直圧法に分類される。
4.直達牽引法は柔道整復師が汎用する方法である。
解答1
解説
1.〇 正しい。牽引直圧法は、最初に捻転転位を除去する。なぜなら、牽引直圧整復法は、主に引っ張る力を利用するため。回転や捻転した骨を元の位置に戻すには限界がある。
・牽引直圧整復法とは、一般的な骨折の整復法(治療)のひとつである。徒手整復法で最も用いられる非観血的整復法である。方法として、骨折端に直接圧力を加える。したがって、骨折で高度な捻転転位がある場合、整復するのは困難である。また、末梢方向へ牽引するときは、急激な牽引力を加えると骨の軟部組織に損傷を起こすため、持続的で緩徐に牽引する。
2.× 屈曲整復法は筋緊張を「増強」ではなく減弱させて行う。なぜなら、筋を緊張させてしまうと、骨折端がさらに離開して整復が困難になるため。
・屈曲整復法とは、短縮転位の整復困難な横骨折に適応される整復方法である。この整復法では、最も緊張が強く整復操作を妨害している骨膜や筋の緊張を取り除き整復を容易にすることを目的とする。
3.× ハンギングキャスト法は、「牽引直圧法」ではなく牽引自重法である。
・牽引直圧法とは、骨折端に直接圧力を加えることで治療する整復法である。
・ハンギングキャストとは、主に上腕骨骨幹部骨折(一部、ずれのある上腕骨近位端骨折)に用いられ、脇の下から手部までギブスをまいてその重みで整復する。
4.× 「直達牽引法」ではなく介達牽引法は、柔道整復師が汎用する方法である。なぜなら、直達牽引法とはピンや鋼線を骨に刺入して行う観血的牽引法であり、皮膚を切開または貫通させる行為(=医行為)に該当するため。したがって、医師以外(柔道整復師など)には認められていない。柔道整復師が行えるのは非観血的整復法(徒手整復・牽引直圧法・屈曲整復法・介達牽引など)である。
牽引とは、持続的に引っ張って負荷をかけることで、骨折を整復する治療法である。骨折により転位している骨を持続的に牽引することで、転位を治し整復する。①直達牽引と②介達牽引の2種類がある。
①直達牽引とは、骨に直接牽引力を働かせる方法をという。
②介達牽引とは、骨に直接牽引力を加えず、皮膚や筋肉を介して骨に力を加える牽引法である。皮膚に絆創膏や包帯を巻いて牽引を行う。
 国試オタク
国試オタク