この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問71 非抱合(間接)ビリルビンを抱合(直接)ビリルビンに変化させるのはどれか。
1.脾臓
2.肝臓
3.胆嚢
4.腎臓
答え.2
解説
(総)ビリルビンとは、赤血球が壊れたときにできる黄色い色素のことである。総ビリルビンは、①間接ビリルビンと②直接ビリルビンをあわせていう。基準値:0.2〜1.2mg/dLである。肝細胞の障害により、直接ビリルビンが上昇する。急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がん、自己免疫性肝炎などがあげられる。腎臓からも排泄され、主に肝臓で代謝されるため、肝臓や胆嚢の状態を知るための重要な指標となる。
1.× 脾臓とは、①古くなった血球(白血球、赤血球、血小板)の処理や、②感染に対する防御など免疫に関係する働きを担う。
2.〇 正しい。肝臓は、非抱合(間接)ビリルビンを抱合(直接)ビリルビンに変化させる。肝臓とは、有害物質を無毒化し排泄する臓器である。ほかにも①代謝、②貯蔵、③胆汁の生成・排泄、④生体防御の働きを持つ。
3.× 胆嚢とは、胆汁を貯蔵し、必要に応じて腸に放出する役割を持つ臓器である。肝臓の右葉の下に位置し、長さは10cm、幅は4cm程度で、50〜60mlの胆汁を貯えることができる。
4.× 腎臓とは、老廃物や余分な水分、塩分などを尿として排泄することで、体の中の水分量やナトリウムやカリウムといったイオンバランスを適正に保ったり、血液の酸性・アルカリ性を調節したり、体内を常に最適な環境にする機能がある。
問72 熱中症への応急対応で誤っているのはどれか。
1.冷水を飲ます。
2.解熱薬を投与する。
3.日陰に移動させる。
4.身体を水で濡らして扇ぐ。
答え.2
解説
熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指す。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもある。主な初期症状として、めまい(目眩、眩暈)や立ちくらみ、一時的な失神などがあげられる。
1.3~4.〇 正しい。冷水を飲ます/日陰に移動させる/身体を水で濡らして扇ぐ。
これらは、熱中症への応急対応である。身体を冷やすために、冷たい水を飲ませたり、水をかけたり濡らしたタオルを使って体を冷やし、体内の温度を下げ、水分を補給する。また、日陰に移動させることで、直接の暑さを避け、体温の上昇を防ぐ。
2.× 解熱薬を投与する必要はない。なぜなら、熱中症は体内の熱がこもってしまうことが原因であるため。つまり、熱中症は外気温が原因で体温が上がっている状態であるため。解熱剤の適応は、病気(感染症など)による発熱である。
問73 クリアランスが糸球体濾過量の指標と成るのはどれか。
1.尿素
2.イヌリン
3.グルコース
4.パラアミノ馬尿酸
答え.2
解説
糸球体濾過量とは、腎臓の機能を表す指標で「GFR(Glomerular Filtration Rate)」とも呼ばれる。腎臓のなかにある糸球体(毛細血管の集合体)が1分間にどれくらいの血液を濾過して尿を作れるかを示している。推算糸球体濾過量(eGFR)の正常値は、「60ml/分/1.73㎡以上」で、年齢、性別、血清クレアチニン値、シスタチンC値から計算する。①正常(G1:90以上)、②軽度低下(G2:60〜89)、③中等度低下(G3a:45〜59、G3b:30〜44)、④高度低下(G4:15〜29)、⑤末期腎不全(G5:15以下)に分類される。
1.× 尿素とは、動物の尿中に含まれる有機化合物であり、たんぱく質や核酸の分解生成物中の窒素分を体外に排出する役割を受け持っている。検査値が高い場合、腎臓のはたらきが悪くなっていることが考えられ、逆に低い場合、尿素を作る肝臓の働きが悪くなっているか、タンパク質の摂取が極端に少ないことなどが考えられる。
2.〇 正しい。イヌリンは、クリアランスが糸球体濾過量の指標と成る。イヌリンとは、糸球体漁過量を測定する指標としてよく用いられる。健常成人では約 100mL/分/1.73m2とされている。ただし、日本では、種々の事情により、実地診療(保険診療)には導入されていない。
3.× グルコースは、正常な尿にほとんど含まれない。なぜなら、グルコースが尿中に存在する場合は、糖尿病などの病的状態が疑われるため。健常者の場合、腎臓の糸球体でグルコースは濾過されるが、通常は腎臓の近位尿細管でほぼ完全に再吸収されるため、正常な尿中にはほとんど検出されない。ちなみに、グルコースとは、血液中の主要な糖分であり、脳のエネルギー源として関与する。
4.× パラアミノ馬尿酸とは、腎血漿流量の測定に使用される。糸球体で濾過され、尿細管で分泌されるが、再吸収はされない物質であり、血液が腎臓を通過することによりその90%が尿中に排出される。
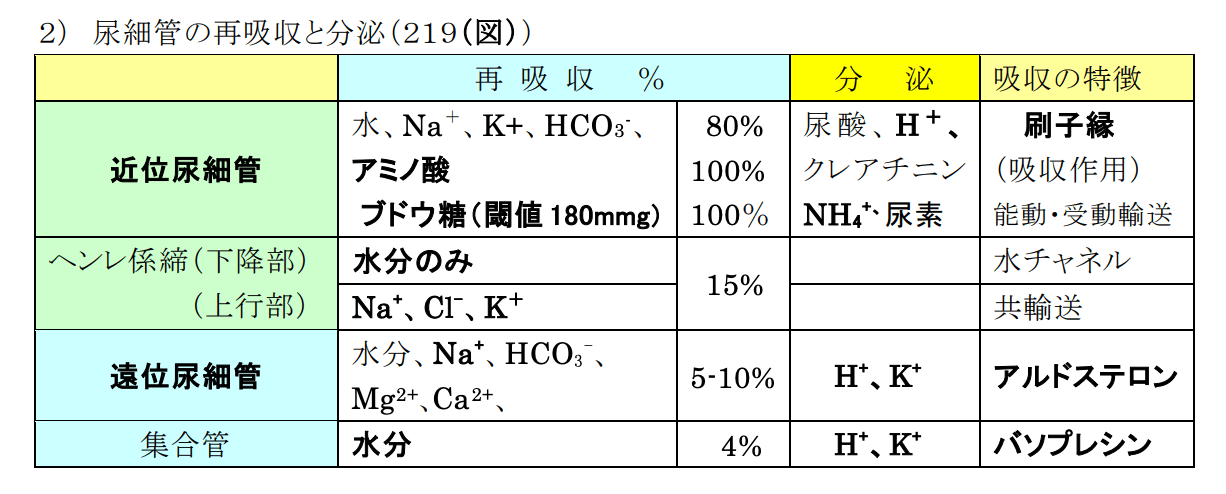
(図引用: 泌尿器のしくみと働き )
問74 視床下部で合成されるホルモンはどれか。
1.オキシトシン
2.サイロキシン
3.コルチゾール
4.エリスロポエチン
答え.1
解説
1.〇 正しい。オキシトシンは、視床下部で合成されるホルモンである。ちなみに、脳下垂体後葉から分泌される。乳汁射出、子宮収縮作用がある。また、分娩開始前後には分泌が亢進し、分娩時に子宮の収縮を促し、胎児が下界に出られるように働きかける。
2.× サイロキシンとは、甲状腺ホルモンのひとつで、甲状腺にて合成される。甲状腺ホルモンとは、サイロキシン(T4)とトリヨードサイロニン(T3)があり、新陳代謝を調節している。脈拍数や体温、自律神経の働きを調節し、エネルギーの消費を一定に保つ働きがある。
3.× コルチゾールとは、副腎皮質で合成、副腎皮質から分泌されるホルモンで、血糖値の上昇や脂質・蛋白質代謝の亢進、免疫抑制・抗炎症作用、血圧の調節など、さまざまな働きがあるが、過剰になるとクッシング症候群、不足するとアジソン病を引き起こす。
4.× エリスロポエチンとは、主に腎臓で合成され、腎臓から分泌される糖蛋白性の造血促進ホルモンである。
問75 ホルモンとその欠乏による症状の組合せで誤っているのはどれか。
1.成長ホルモン:低身長
2.エストロゲン:骨粗鬆症
3.インスリン:糖尿病
4.甲状腺ホルモン:アジソン病
答え.4
解説
1.〇 正しい。成長ホルモン:低身長
・成長ホルモンとは、下垂体前葉から合成・分泌されるホルモンで、成長促進作用や代謝作用などの作用がある。
2.〇 正しい。エストロゲン:骨粗鬆症
・エストロゲンとは、主に卵巣から分泌される女性らしさをつくるホルモンで、成長とともに分泌量が増え、生殖器官を発育・維持させる働きをもっている。女性らしい丸みのある体形をつくったり、肌を美しくしたりする作用もあるホルモンである。分泌量は、毎月の変動を繰り返しながら20代でピークを迎え、45~55歳の更年期になると急激に減る。
3.〇 正しい。インスリン:糖尿病
・インスリンとは、膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞から分泌されるホルモンの一種で、①血糖低下、②脂肪合成の作用がある。
4.× 甲状腺ホルモンの欠乏は、「アジソン病」ではなく橋本病である。
・甲状腺ホルモンとは、サイロキシン(T4)とトリヨードサイロニン(T3)があり、新陳代謝を調節している。脈拍数や体温、自律神経の働きを調節し、エネルギーの消費を一定に保つ働きがある。
・アジソン病とは、副腎皮質機能低下症ともいい、るいそう(やせ)と色素沈着など特徴的である。副腎皮質ホルモンには、コルチゾール・アルドステロン・アンドロゲン(男性ホルモン)などがある。コルチゾール:血糖値の上昇や脂質・蛋白質代謝の亢進、免疫抑制・抗炎症作用、血圧の調節など、さまざまな働きがあるが、過剰になるとクッシング症候群、不足するとアジソン病を引き起こす。
更年期障害とは、更年期に出現する器質的な変化に起因しない多彩な症状によって、日常生活に支障をきたす病態と定義される。更年期症状は大きく、①自律神経失調症状、②精神神経症状、③その他に分けられるが、各症状は重複して生じることが多い。治療の一つに、ホルモン補充療法(HRT)があげられる。ホルモン補充療法とは、エストロゲン(卵胞ホルモン)を補うことで、更年期障害を改善する治療法である。ほてり、のぼせ、発汗などといった代表的な症状に高い効果を示す。禁忌として、エストロゲン依存性悪性腫瘍(子宮内膜癌、乳癌)またその疑いのあるもの、重症肝機能障害、血栓性疾患などがあげられる。
 国試オタク
国試オタク 
