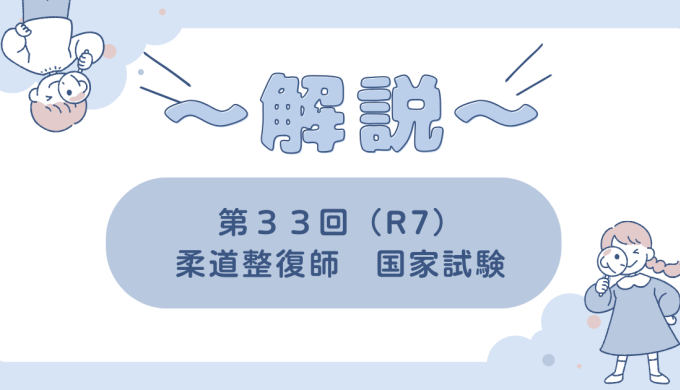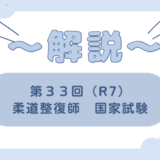この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題46 医師の守秘義務違反が規定されているのはどれか。
1.刑法
2.医師法
3.医療法
4.薬事法
解答1
解説
1.〇 正しい。刑法は、医師の守秘義務違反が規定されている。
・刑法とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 刑法には、医師・薬剤師・助産師などに対し、職務上の秘密を漏らした場合の罰則規定があるが、保健師は含まれていない。(刑法第134条)医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以上の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2.× 医師法とは、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律である。つまり、一般人には禁止されている医療行為を、医師という有資格者に限って許可する法律である。
3.× 医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。
4.× 薬事法とは、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品などの有効性、安全性、品質等の確保を目的として、一定の基準や取り扱いを定め、必要な規制を行うための法律である。
問題47 医師法で規定されているのはどれか。
1.応招義務はない。
2.未成年者には免許を与えない。
3.無診察でも処方箋は交付できる。
4.診療録の保存期間は10年である。
解答2
解説
1.× 応招義務はある「ことが規定されている」。応招義務とは、医師や歯科医師が診察治療の求めがあった場合に、正当な理由がなければ診療を拒んではならないという義務である。医師・歯科医師・薬剤師・助産師が該当する。
・(参考)医師法第19条第2項(応招義務等):診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
2.〇 正しい。未成年者には免許を与えない。第三条において、「未成年者には、免許を与えない」と記載されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 無診察でも処方箋は交付「できない」。第二十条において「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない」と記載されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。
4.× 診療録の保存期間は、「10年」ではなく5年である。第二十四条 2において、「診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない」と記載されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。
問題48 業務独占がない資格はどれか。
1.医師
2.薬剤師
3.作業療法士
4.診療放射線技師
解答3
解説
業務独占とは、国家資格を持たないものが、その名称を用いて当該業務に従事することはできないこと(例:医者など)。一方、名称独占資格とは、資格がなくてもその業務に従事する事はできるが、資格取得者のみ特定の資格名称(肩書き)を名乗ることができ、資格を所有していない者が法律に定める特定の名称を名乗ることができない資格のことをいう。つまり、作業療法士の仕事は、資格を無くても行うことができるが、「私は作業療法士です」と名乗ることはできないということである。
1.〇 医師は、業務独占がある。
・医師とは、患者の容態・問診・検査データなどから病名と病状を確定する診断と、投薬や手術などにより病状を改善させる治療を行う専門職種である。これは医師法により定められている行為で、医師だけに許されている。
2.〇 薬剤師は、業務独占がある。
・薬剤師とは、厚生労働大臣の免許を受けた国家資格で、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる職種である。
3.× 作業療法士は、業務独占がない資格である。作業療法士は、名称独占資格である。
・名称独占資格とは、資格がなくてもその業務に従事する事はできるが、資格取得者のみ特定の資格名称(肩書き)を名乗ることができ、資格を所有していない者が法律に定める特定の名称を名乗ることができない資格のことをいう。つまり、作業療法士の仕事は、資格を無くても行うことができるが、「私は作業療法士です」と名乗ることはできないということである。
4.〇 診療放射線技師は、名称独占と業務独占である。
・診療放射線技師とは、放射線技術の専門知識を生かして、放射線や検査の説明、目的に応じた撮影、三次元画像などの作成や読影の補助、診療上の説明を受ける方へ判りやすい画像提供など、手術サポートおよび放射線治療などを行う専門職である。
問題49 理学療法士法における業はどれか。
1.音声機能の維持向上
2.治療体操の実施
3.捻挫部位の施術
4.義肢の調整
解答2
解説
理学療法士とは、医師の指示のもとに治療体操や運動・マッサージ・電気刺激・温熱などの物理的手段を用いて、運動機能の回復を目的とした治療法・物理療法(理学療法)を行う専門職である。つまり、関節可動域や筋力の向上などが役割である。
1.× 音声機能の維持向上は、主に言語聴覚士が行う。
・言語聴覚士とは、言語や聴覚、音声、呼吸、認知、発達、摂食・嚥下に関わる障害に対して、その発現メカニズムを明らかにし、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援などを行う専門職である。
2.〇 正しい。治療体操の実施は、理学療法士法における業である。理学療法士及び作業療法士法の第二条(定義)において、「この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」と記載されている(※引用:「理学療法士及び作業療法士法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 捻挫部位の施術は、主に柔道整復師が行う。柔道整復の対象疾患は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれ等。骨折及び脱臼については、医師の同意が必要。(応急手当を除く)(※引用:「柔道整復に係る療養費の概要」厚生労働省様HPより)
4.× 義肢の調整は、主に義肢装具士が行う。義肢装具士とは、法律上、「医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者」と定められ、医師の処方に従い患者さんの採型や採寸を行い、これを元に義肢装具を製作して、病院などで適合を行う。
問題50 医療法上の病床でないのはどれか。
1.精神病床
2.特養病床
3.療養病床
4.感染症病床
解答2
解説
医療法上の「療養病床」は、長期療養が必要な患者さんを受け入れる病床で、病院や診療所に設置される。
1.〇 精神病床は、医療法上の病床である。医療法第7条第2項が根拠である。
・精神病床とは、病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。
2.× 特養病床は、医療法上の病床でない。なぜなら、「特養」は、「特別養護老人ホーム」の略であり、これは病気の治療を主とする病院ではなく、寝たきりや認知症などで常時介護が必要な高齢者が入所して生活する介護施設であるため。
3.〇 療養病床は、医療法上の病床である。医療法第7条第2項が根拠である。
・療養病床とは、病院又は診療所の病床のうち(前三号に掲げる病床以外の病床)、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。
4.〇 感染症病床は、医療法上の病床である。医療法第7条第2項が根拠である。
・感染症病床とは、指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。
 国試オタク
国試オタク