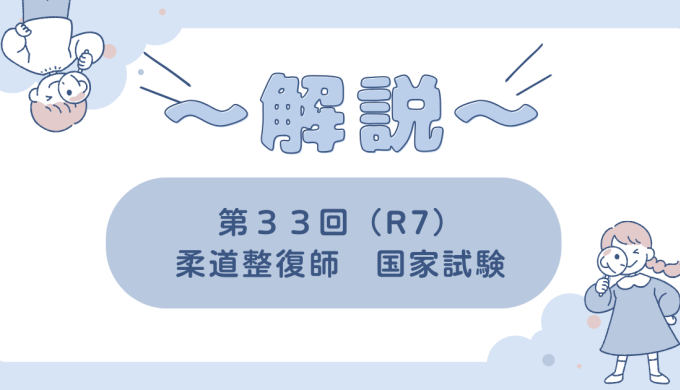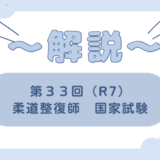この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題6 定型的鎖骨骨折の坐位整復法で第2助手が行うのはどれか。
1.骨折部に直圧を加える。
2.患者の顔色の変化をみる。
3.患者の胸郭を拡大させる。
4.患側の前腕と手指を保持する。
解答2
解説
定型的鎖骨骨折は、近位骨片が胸鎖乳突筋の作用で後上方に転移するものをさす。
【坐位整復法】
・患者:坐位または椅子に腰かけさせる(肘関節90度屈曲位)。
・第1助手:患者の後方に位置して背柱部に膝頭を当てがい両脇に手を入れて両肩を外後方へ引き、短縮転位を取り除く。
・第2助手:患肢の上腕および前腕を把握して上腕と肩甲骨を上外方に持ち上げて下方転位の遠位骨片を近位骨片に近づける。
・術者:術者は前方(やや患側)に位置し、骨折部を前下向へ圧迫し整復する。
1.× 骨折部に直圧を加える。
これは、術者が行う。
2.〇 正しい。患者の顔色の変化をみる。
これは、第2助手が行う重要な役割である。ただし、第2助手だけが行うのではなく、それぞれができる範囲で患者の状態・変化に配慮すべきである。
3.× 患者の胸郭を拡大させる。
これは、第1助手が行う。
4.× 患側の「前腕と手指」ではなく肘と前腕遠位を保持する。
・第2助手は、肘関節90°屈曲位で肘部と前腕遠位部を把握する。
問題7 上腕骨外科頸外転型骨折の診察で誘導後の手順はどれか。
①整復の準備
②損傷部の確認
③全身状態の観察
1.①→②→③
2.①→③→②
3.②→①→③
4.③→②→①
解答4
解説
1.× ①→②→③
2.× ①→③→②
3.× ②→①→③
これらの手順より優先されるものが他にある。
4.〇 正しい。③→②→①は、上腕骨外科頸外転型骨折の診察で誘導後の手順である。
③全身状態の観察→②損傷部の確認→①整復の準備の手順が最も合理的である。
基本的な流れは、まず患者の「全身状態」を迅速に把握し(生命の危機に関わる問題がないか)、次に「損傷部」の詳細な診察や検査を行い、骨折の種類や合併症の有無などを正確に診断し、最後にその診断に基づいて必要な治療(この場合は「整復の準備」)を行うという順序である。この流れは、患者さんの安全を第一に考えた標準的な手順であり、上腕骨外科頸外転型骨折に限らず、ほとんどの外傷に対応する際の基本となる。
例えば、病院に到着した患者に対し、まずバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸、体温)を測定し、意識レベルを確認する(全身状態の観察)。次に、痛みを訴えている肩や腕の変形、腫れ、感覚や運動の異常などを調べ、レントゲン撮影を行う(損傷部の確認)。これらの情報から骨折の状態を診断し、整復が必要であれば、麻酔医の準備や必要な器具の手配などを進める(整復の準備)。
問題8 上腕骨外科頸外転型骨折で誤っているのはどれか。
1.三角筋の膨隆は消失する。
2.上腕軸の骨折端部は内方へ向く。
3.噛合骨折では自動運動が可能である。
4.皮下出血斑は上腕内側部から前胸部に出現する。
解答1
解説
上腕骨外科頸骨折とは、上腕骨の骨折の中で、特に高齢者に多く発生する骨折の一つであり、骨頭から結節部にかけての太い部分から骨幹部に移行する部位で発生する。老年期とは、一般的に65歳以上をいう。
患者:背臥位、腋窩に手挙大より大きめの枕子を挿入しておく。
第1助手:帯などで上内方に牽引、固定させる。
第2助手:肘関節直角位で上腕下部及び前腕下部を把握する。末梢牽引させながら徐々に上腕を外転させ短縮転位を除去し両骨折端を離開させる。
術者:両手で遠位骨片近位端を把握する。
(対向牽引が遠位骨片骨軸方向に正しく行う)
1.× 三角筋の膨隆は、「消失」ではなく著明となる。なぜなら、骨折部位周辺の組織が損傷し、炎症や出血が起こるため。
2.〇 正しい。上腕軸の骨折端部は、内方へ向く。ちなみに、内転型はその逆となる。
【上腕骨外科頸外転型骨折の転位・変形】
・近位骨片は軽度内転
・遠位骨片は軽度外転
・遠位骨折端は前内上方へ転位
・骨折部は前内方凸の変形
3.× 噛合骨折では自動運動が可能であるのは、「上腕骨解剖頸骨折」である。上腕骨解剖頸骨折は、転位・変形は少ない。噛合骨折の場合はわずかに転位し短縮する。固定する際は、肩関節外転70~80°、水平屈曲30~40°で固定する。予後は、噛合骨折の場合に良好である。ただし、高齢者では癒合困難なことが多く、長期固定による関節拘縮をきたし、肩関節の機能障害を残す。阻血性骨頭壊死、外傷性関節炎などを生じることがある。
4.× 皮下出血斑は、「上腕内側部から前胸部」ではなく骨折部位に出現する。
・皮下出血斑とは、皮下出血(内出血)したときに紫色のアザのことである。紫斑病ともいう。内出血が起こるメカニズムは、何かにぶつかるなど外部からの衝撃が身体に加わることにより皮膚や皮下の組織が壊れてしまい出血が身体の内部だけに溜まることで起こる。つまり、原因としては転倒などによる打撲や打ち身、捻挫が多く、ひどい肉離れなどでみられる。
発生機序:肩外転位で手掌、肘を衝いて転倒
鑑別疾患:肩関節前方脱臼
好発年齢層:高齢者
腱板損傷:棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋
整復前の確認:腋窩動脈(橈骨動脈)、腋窩神経の確認
【上腕骨外科頸外転型骨折の転位・変形】
・近位骨片は軽度内転
・遠位骨片は軽度外転
・遠位骨折端は前内上方へ転位
・骨折部は前内方凸の変形
問題9 コーレス(Colles)骨折の牽引直圧整復法で誤っているのはどれか。
1.転位軽度な骨折に対して行う。
2.遠位骨片背側から圧をかける。
3.遠位骨片を過伸展させる。
4.遠位骨片を回内させる。
解答3
解説
コーレス骨折(橈骨遠位端部伸展型骨折)は、橈骨遠位端骨折の1つである。 橈骨が手関節に近い部分で骨折し、遠位骨片が手背方向へ転位する特徴をもつ。合併症には、尺骨突き上げ症候群、手根管症候群(正中神経障害)、長母指伸筋腱断裂、複合性局所疼痛症候群 (CRPS)などがある。
【屈曲整復法】
①肘関節:90°屈曲(助手:骨折部の近位部を把握固定)
術者:母指を背側に他の4指を掌側にあてがい手根部とともに回内位で軽く牽引する。
②回内位で軽く牽引し、橈側より遠位骨片を圧迫する(捻転転位、橈尺面の側方転位の除去、軸を合わせる)。
術者:軽く牽引をしたまま、遠位骨片に手とともに過伸展を強制する。
③その肢位のまま、両母指で遠位骨片近位端を遠位方向に引き出し、近位骨片遠位端に近づける(腕橈骨筋を弛緩させる、短縮転位を除去)。
④両骨折端背側が接合したのを確認して徐々に遠位骨片を手部とともに掌屈する。その際、両示指で近位骨片端を掌側から両拇指で遠位骨片端を圧迫して整復する(背側転位の除去)。その後の固定は、肘関節90°、手関節軽度掌屈、尺屈、前腕回内位とする。
1.〇 正しい。転位軽度な骨折に対して行う。なぜなら、牽引直圧整復法は、骨折で高度な捻転転位がある場合、整復するのは困難であるため。
2.〇 正しい。遠位骨片背側から圧をかける。なぜなら、牽引直圧整復法の方法は、骨折端に直接圧力を加えるため。
3.△ 遠位骨片を過伸展させる。
・コーレス骨折の屈曲整復法において、途中、遠位骨片に手とともに過伸展を強制する場面はあるが、最後に両骨折端背側が接合したのを確認して徐々に遠位骨片を手部とともに掌屈(屈曲)する。
4.〇 正しい。遠位骨片を回内させる。なぜなら、骨片を解剖学的な位置に戻すため。
・固定は、肘関節90°、手関節軽度掌屈、尺屈、前腕回内位とする。
牽引直圧整復法とは、一般的な骨折の整復法(治療)のひとつである。徒手整復法で最も用いられる非観血的整復法である。方法として、骨折端に直接圧力を加える。したがって、骨折で高度な捻転転位がある場合、整復するのは困難である。また、末梢方向へ牽引するときは、急激な牽引力を加えると骨の軟部組織に損傷を起こすため、持続的で緩徐に牽引する。
問題10 コーレス(Colles)骨折の固定の際に、助手への指示で誤っているのはどれか。
1.整復位を維持させる。
2.再転位がないか確認させる。
3.固定材料がずれないようにさせる。
4.術者が操作しやすい位置で患肢を保持させる。
解答2
解説
コーレス骨折(橈骨遠位端部伸展型骨折)は、橈骨遠位端骨折の1つである。 橈骨が手関節に近い部分で骨折し、遠位骨片が手背方向へ転位する特徴をもつ。合併症には、尺骨突き上げ症候群、手根管症候群(正中神経障害)、長母指伸筋腱断裂、複合性局所疼痛症候群 (CRPS)などがある。
【屈曲整復法】
①肘関節:90°屈曲(助手:骨折部の近位部を把握固定)
術者:母指を背側に他の4指を掌側にあてがい手根部とともに回内位で軽く牽引する。
②回内位で軽く牽引し、橈側より遠位骨片を圧迫する(捻転転位、橈尺面の側方転位の除去、軸を合わせる)。
術者:軽く牽引をしたまま、遠位骨片に手とともに過伸展を強制する。
③その肢位のまま、両母指で遠位骨片近位端を遠位方向に引き出し、近位骨片遠位端に近づける(腕橈骨筋を弛緩させる、短縮転位を除去)。
④両骨折端背側が接合したのを確認して徐々に遠位骨片を手部とともに掌屈する。その際、両示指で近位骨片端を掌側から両拇指で遠位骨片端を圧迫して整復する(背側転位の除去)。その後の固定は、肘関節90°、手関節軽度掌屈、尺屈、前腕回内位とする。
1.〇 正しい。整復位を維持させる。なぜなら、ずれた骨片を正しい位置に戻した後、その整復された位置(整復位)を保ったまま固定することが、骨折の治癒において重要であるため。
2.× 再転位がないか確認することは、「術者」が行うため。この確認には、X線画像の読影や、骨の解剖学的な知識に基づいた触診など、専門的な知識と経験が必要である。
3.〇 正しい。固定材料がずれないようにさせる。なぜなら、固定材料がずれている場合、骨折部の安定性が損なわれ、治癒過程に支障をきたすため。
4.〇 正しい。術者が操作しやすい位置で患肢を保持させる。なぜなら、助手は、術者が正確かつ効率的に固定操作を行えるようサポートするため。したがって、骨折した腕や手首が、術者にとって最も作業しやすい高さ、角度、向きに保持されている必要がある。
 国試オタク
国試オタク