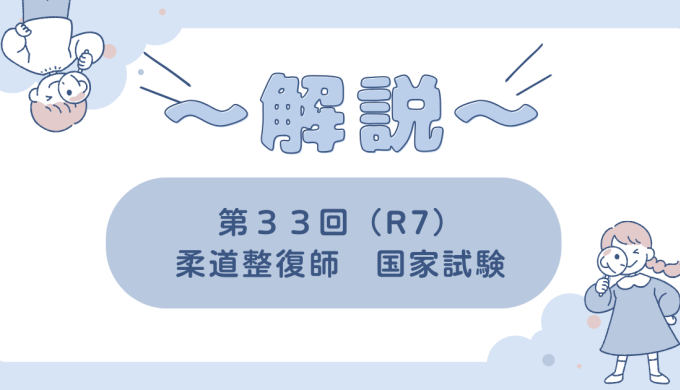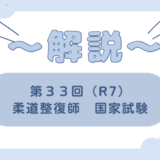この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題11 コーレス(Colles)骨折の固定後の確認で誤っているのはどれか。
1.固定具の圧迫による疼痛の増加がないか。
2.MP関節とIP関節の運動が可能であるか。
3.運動性神経機能評価のために爪圧迫検査をしたか。
4.帰宅後緊縛包帯の症状が現れた場合の処置を指導したか。
解答3
解説
合併症:舟状骨骨折、尺骨茎状突起骨折、月状骨脱臼 、遠位橈尺関節離解、神経損傷などが生じる。
続発症・後遺症:長母指伸筋腱の断裂、手根管症候群、変形癒合、変形性関節症、指~肩関節の拘縮、反射性交感神経性ジストロフィー、前腕の回内・回外運動障害、橈骨遠位骨端軟骨損傷による成長障害、橈骨・尺骨・正中神経麻痺などが生じる。
固定肢位:肘関節直角屈曲、前腕回内、手関節軽度屈曲・軽度尺屈位で、上腕近位部からMP関節手前まで4~5週間固定する。
1.〇 正しい。固定具の圧迫による疼痛の増加がないか。
なぜなら、固定具がきつすぎると、皮膚や軟部組織が圧迫されて血行が悪くなったり、神経が締め付けられたりして、痛みが強くなることがあるため。
2.〇 正しい。MP関節とIP関節の運動が可能であるか。なぜなら、コーレス骨折の固定は、「上腕近位部からMP関節手前まで」であるため。MP関節とIP関節の運動が可能であることは、関節拘縮や循環障害(浮腫)の予防につながる。
3.× 「運動性神経機能評価」ではなく循環機能のために爪圧迫検査する。爪圧迫テスト(毛細血管再充満時間)とは、指先の爪床を圧迫して血液が再充満するまでの時間を測定する、末梢循環の状態を評価する検査方法である。一般的には、爪を5秒間圧迫して離し、爪の赤みが戻るまでの時間を計測する。
4.〇 正しい。帰宅後、緊縛包帯の症状が現れた場合の処置を指導したか。なぜなら、ギプスなどの固定をした後、時間の経過とともに患部が腫れてきて固定がきつくなり、神経や血管が圧迫されて血行障害や神経障害を引き起こす可能性があるため。これらの重篤な合併症を防ぐためには、帰宅後に患者さん自身やご家族が異常に気づき、適切に対応できるよう、注意すべき症状(強い痛み、痺れ、指の色や温度の変化など)と、その場合の対処法(例えば、固定を少し緩める、患肢を高く上げる、そして何よりもすぐに医療機関に連絡すること)を事前にしっかりと指導しておく。
問題12 第5中手骨頸部骨折の副子固定で正しいのはどれか。
1.綿花は背側にあてる。
2.固定期間は2週とする。
3.手関節の固定は屈曲位とする。
4.固定範囲は前腕遠位からPIP関節までとする。
解答1
解説
固定の主たる目的は、MP 関節を屈曲位として末梢骨片を安定させることである。固定は様々あるが、症状にあった固定を行なう必要がある。
◎ 固定時の留意点
1、指関節背側の皮膚は薄く、屈曲により皮膚血流が悪くなりやすい、したがって、皮膚潰瘍や壊死を起こしやすい。
2、ガーゼなどを使用することで、皮膚の保護に十分注意する必要がある。
3、高齢者で転位を避けるために PIP 関節の屈曲位を余儀なくされる場合、指の屈曲拘縮を起こしやすいので、可能な範囲で軽度屈曲位を目指す。
4、強度の固定は手指の巧緻運動を著しく障害し、長期にわたって機能障害を残すことになる。
(※引用:「中手骨頚部骨折」著:舘 利幸)
1.〇 正しい。綿花は背側にあてる。なぜなら、指関節背側の皮膚は薄く、屈曲により皮膚血流が悪くなりやすいため。
2.× 固定期間は、「2週」ではなく3週以上(~6週)とする。
3.× 手関節の固定は、「屈曲位」ではなく軽度背屈位とする。MP関節40~70度屈曲位/PIP関節軽度屈曲位/DIP関節軽度屈曲位にて固定する。
4.× 固定範囲は、手関節から「PIP関節」ではなくDIP関節までとする。
固定法は、アルミ副子を掌側にあて、合成樹脂製キャスト材を背側にあてて固定する方法と、アルミ副子を背側にあて、ロール状の枕子を握らせて合成樹脂製キャスト材で固定する方法がある。固定範囲は前腕から末節骨を含め、第5指であれば、隣接指の第4指とともに固定する。
第5中手骨頸部骨折の骨折部は背外側偏位を呈する場合が多い。第5中手骨頸部骨折は末梢骨片が短く且つ中手指節関節に近い事から整復操作後も転位しやすく、観血的療法の適応となる事が少なくない。又、保存的療法の一般的な整復法はJhass法(中手指節関節及び近位指節間関節90度屈曲位にて中手骨骨頭を押し上げる)である。骨折部が最も安定した固定肢位はJhass法施行時の中手指節関節及び近位指節間関節90度屈曲位である。しかし、この肢位は近位指節問関節背側部の血行障害による皮膚壊死や支靱帯の短縮による近位指節問関節の屈曲拘縮をきたしやすく禁忌とされている。渡辺は幅2.5cmの非伸縮性粘着テープを用いて中手指節関節及び近位指節間関節90度屈曲位で固定し、良好な治療成績を挙げている。(※引用:「第5中手骨頸部骨折に対する整形理学療法」著:有川整形外科医院)
問題13 第5中手骨頸部骨折で正しいのはどれか。
1.骨頭に牽引をかけて固定する。
2.整復後は尺骨動脈の拍動を確認する。
3.固定中は爪面の向きを隣接指と比較する。
4.軽度な屈曲転位の残存でも動作時痛が生じる。
解答3
解説
固定の主たる目的は、MP 関節を屈曲位として末梢骨片を安定させることである。固定は様々あるが、症状にあった固定を行なう必要がある。
◎ 固定時の留意点
1、指関節背側の皮膚は薄く、屈曲により皮膚血流が悪くなりやすい、したがって、皮膚潰瘍や壊死を起こしやすい。
2、ガーゼなどを使用することで、皮膚の保護に十分注意する必要がある。
3、高齢者で転位を避けるために PIP 関節の屈曲位を余儀なくされる場合、指の屈曲拘縮を起こしやすいので、可能な範囲で軽度屈曲位を目指す。
4、強度の固定は手指の巧緻運動を著しく障害し、長期にわたって機能障害を残すことになる。
(※引用:「中手骨頚部骨折」著:舘 利幸)
1.× 骨頭に「牽引」ではなく「適度な圧迫」をかけて固定する。なぜなら、牽引により骨折部位が離開してしまう恐れがあるため。
2.× 整復後は、「尺骨動脈の拍動」ではなく爪圧迫検査にて確認する。なぜなら、第5中手骨頸部骨折において、尺骨動脈の拍動(手首)は、受傷部位から近位側となるため。循環障害を疑う場合、受傷部位より遠位で確認することが望ましい。
3.〇 正しい。固定中は、爪面の向きを隣接指と比較する。なぜなら、手指や中手骨の骨折で最も注意すべき合併症の一つに、回転転位(指が軸を中心にねじれてずれること)があるため。回転転位があると、指を曲げたときに隣の指と重なったり、不自然な方向を向いたりして、指の機能に著しい障害を残しやすい。
4.× 必ずしも、軽度な屈曲転位の残存でも動作時痛が生じる「とはいえない」。特に、小指の中手骨は、他の指に比べて多少の角度変形が許容されやすい部位とされている。
第5中手骨頸部骨折の骨折部は背外側偏位を呈する場合が多い。第5中手骨頸部骨折は末梢骨片が短く且つ中手指節関節に近い事から整復操作後も転位しやすく、観血的療法の適応となる事が少なくない。又、保存的療法の一般的な整復法はJhass法(中手指節関節及び近位指節間関節90度屈曲位にて中手骨骨頭を押し上げる)である。骨折部が最も安定した固定肢位はJhass法施行時の中手指節関節及び近位指節間関節90度屈曲位である。しかし、この肢位は近位指節問関節背側部の血行障害による皮膚壊死や支靱帯の短縮による近位指節問関節の屈曲拘縮をきたしやすく禁忌とされている。渡辺は幅2.5cmの非伸縮性粘着テープを用いて中手指節関節及び近位指節間関節90度屈曲位で固定し、良好な治療成績を挙げている。(※引用:「第5中手骨頸部骨折に対する整形理学療法」著:有川整形外科医院)
問題14 肋骨骨折の固定材料で適切でないのはどれか。
1.さらし
2.ギプス包帯
3.バストバンド
4.非伸縮性絆創膏
解答2
解説
肋骨骨折の屋根瓦状絆創膏固定とは、絆創膏を貼付する範囲をアルコール綿で消毒し、呼気時に貼付していく。その際、乳頭部はガーゼで保護し、肋骨弓下縁から上方に向かって少しずつ重ねながら貼付していく。
1.〇 正しい。さらしとは、柔軟性のある布状の材料である。患者の胸郭に巻き付けることで、体格や骨折部位に合わせて適度な圧迫と固定を加えることができる。
2.× ギプス包帯は、肋骨骨折の固定材料で適切でない。なぜなら、ギプス包帯は硬く固まる性質があるため。胸郭全体に巻いてしまうと、呼吸に必要な胸郭の膨らみや動きが制限してしまう。
・肋骨骨折の固定は、痛みの軽減が主な目的であり、呼吸機能を妨げるような過度な固定は避けるべきである。
3.〇 正しい。バストバンドとは、伸縮性のある素材でできた胸部固定帯である。胸郭全体を広く覆って適度な圧迫と固定を加えることができる。
4.〇 正しい。非伸縮性絆創膏(医療用テープなど)を、骨折した肋骨に沿って皮膚に直接貼ることで、骨折部の局所的な動きを制限し、痛みを軽減する効果が期待できる。
問題15 単数の肋骨骨折で正しいのはどれか。
1.深呼吸で疼痛が増悪する。
2.軋轢音は生じにくい。
3.叩打痛はみられない。
4.動揺性胸郭となる。
解答1
解説
1.〇 正しい。深呼吸で疼痛が増悪する。なぜなら、肋骨は呼吸運動に合わせて動くため。深呼吸により、骨折した肋骨が引っ張られたり、骨折部が動いたりして、痛みが著しく増強する。
2.× 軋轢音は「生じやすい」。なぜなら、肋骨骨折の場合、呼吸や体動によって骨折部が動くため。
・軋轢音とは、骨折した骨の断端同士が動いて擦れ合う際に生じる音や感触のことである。
3.× 叩打痛は「みられる」。なぜなら、肋骨骨折の場合、肋骨は叩打すると、動きやすく、骨の周りにある神経や組織を刺激し、痛みを引き起こすため。
・叩打痛とは、骨折した部分を軽く叩いたり、その周囲を叩いたりすると、骨折部に響いて生じる痛みである。
4.× 動揺性胸郭「とはならない」。なぜなら、単数の肋骨骨折では、胸郭全体の安定性は保たれているため。
・動揺性胸郭とは、通常3本以上の肋骨が連続して、それぞれが2ヶ所以上骨折することで、その部分の胸郭が周囲の胸郭と独立して動き、呼吸運動とは逆の動き(奇異呼吸)をする重篤な状態を指す。
 国試オタク
国試オタク