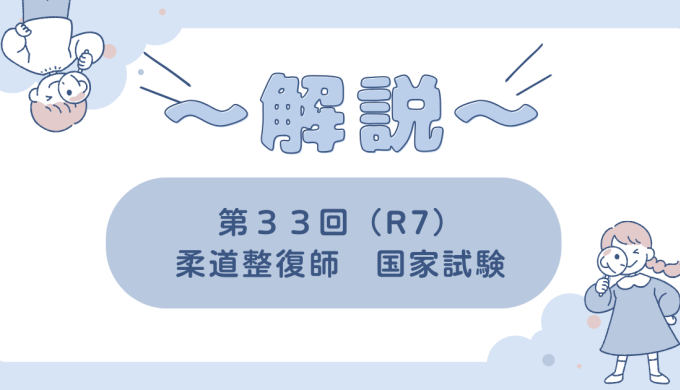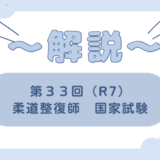この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題16 肋骨骨折の固定で正しいのはどれか。
1.固定期間は6週とする。
2.助手は患者の前方に立つ。
3.吸気状態で息を止めさせて行う。
4.深呼吸ができるように固定する。
解答2
解説
1.× 固定期間は、「6週」ではなく3~4週間とする。なぜなら、肋骨骨折の固定は、痛みの軽減が主な目的であるため。痛みが軽減すれば、その期間内で固定を終了したり、緩めたりすることが多い。
2.〇 正しい。助手は患者の前方に立つ。肋骨骨折の固定(例えばバストバンドやさらしを巻く場合)は、患者の胸郭に固定材料を巻き付けて行う。術者が患者さんの側面や背中側から固定材料を回していく際に、助手は患者さんの前面に立つことで、固定材料を術者から受け取ったり、患者さんの体を支えたり、固定の具合を確認したりといった補助を効率的に行うことができる。
3.× 「吸気」ではなく呼気状態で息を止めさせて行う。なぜなら、呼気状態は、胸郭が最も小さくなった状態であるため。もし、吸気時(胸郭が最大限に広がった状態)で固定してしまうと、呼気により、固定が緩んでしまうため。
4.× 必ずしも、深呼吸ができるように固定する必要はない。なぜなら、「深呼吸ができるように」という表現は、固定が緩すぎて痛みの軽減効果が不十分となりやすいため。適切な固定は、痛みを和らげつつ、肺炎などの合併症を防ぐために、ある程度の胸郭の動きを許容する、バランスの取れた固定を目指す。
問題17 右肩鎖関節上方脱臼患者の衣服着脱の介助で正しいのはどれか。
1.右から脱がせ、左から着せる。
2.右から脱がせ、右から着せる。
3.左から脱がせ、左から着せる。
4.左から脱がせ、右から着せる。
解答4
解説
右肩鎖関節上方脱臼患者
→右手が患側、左手が健側の衣服着脱の介助をおさえておこう。
どちらから、先に手を通すと、関節可動域が少なくて済むか考えられるようにしよう。
1.× 右から脱がせ、左から着せる。
2.× 右から脱がせ、右から着せる。
基本的に「左(健側)」から脱がせる。なぜなら、脱臼している痛い方(右肩)から、先に服を脱がせようとすると、右肩に大きな関節運動を強いることになるため。
3.× 左から脱がせ、左から着せる。
4.〇 正しい。左から脱がせ、右から着せる。
基本的に「右(患側)」から着させる。なぜなら、脱臼している痛い方(右肩)から、先に袖を通すことで、患側への負担を最小限にすることができるため。
問題18 肩鎖関節脱臼の固定で正しいのはどれか。
1.絆創膏固定法では肩峰を圧迫する。
2.包帯固定では胸十字帯法を用いる。
3.枕子で鎖骨近位端を下方へ圧迫する。
4.上腕を長軸方向に持ち上げて固定する。
解答4
解説
【整復法】
①助手は患肢上肢を後上方へ軽く引く。
②術者は下方に転位した患肢上肢を上方に押し上げながら鎖骨遠位端を下方へ圧迫して整復する。
【固定法】
①固定期間:4週~8週
②整復位は困難で完全固定が容易ではない。
1.× 絆創膏固定法では、「肩峰」ではなく鎖骨を圧迫する。肩鎖関節上方脱臼の絆創膏固定法をロバート・ジョーンズという。ロバート・ジョーンズ固定(Robert-Jones固定)は、肩鎖関節上方脱臼の第2~3度損傷で用いる固定法である。
【手順】
①胸部前面を斜めに上行し局所副子上を通過する。
②上腕部後面を通過し綿花沈子をあてた肘をまわる。
③上腕部前面を通過し局所副子上を通過し健側肩甲骨下部まで貼付する。
2.× 包帯固定では、「胸十字帯法」ではなく絆創膏固定法を用いる。
・胸十字帯は、主に胸部や腹部の包帯固定に使用される帯で、胸部に十字状に巻かれる。この方法は、特に胸部や上腹部の外傷や手術後の固定に適している。
3.× 枕子で鎖骨「近位端」ではなく遠位端を下方へ圧迫する。なぜなら、肩鎖関節脱臼で上方にずれるのは、鎖骨の「遠位端」であるため。
4.〇 正しい。上腕を長軸方向に持ち上げて固定する。なぜなら、肩鎖関節上方脱臼は、腕の重みによって鎖骨の遠位端が相対的に下方に引っ張られることで、鎖骨が肩峰の上にずれてしまうことが大きな要因の一つであるため。
問題19 肩関節烏口下脱臼と受傷時の外観が類似するのはどれか。
1.肩峰骨折
2.肩甲骨頸部骨折
3.鎖骨遠位端骨折
4.上腕骨小結節骨折
解答2
解説
烏口下脱臼とは、肩関節前方脱臼(約90%)のひとつである。上腕骨頭が肩甲骨関節窩から前方に脱臼した症状で、①烏口下脱臼と②鎖骨下脱臼に分類される。関節全体を覆う袋状の関節包と靭帯の一部が破れ、突き出た上腕骨頭が烏口突起の下へすべることで起こる脱臼である。介達外力が多く、後方から力が加わる、転倒するなどで手を衝くことで過度の伸展力が発生した場合(外旋+外転+伸展)などに起こる。症状として、①弾発性固定、②関節軸の変化(骨頭は前内方偏位、上腕軸は外旋)、③脱臼関節自体の変形(三角筋部の膨隆消失、肩峰が角状に突出、三角筋胸筋三角:モーレンハイム窩の消失)、④上腕仮性延長、⑤肩峰下は空虚となり、烏口突起下に骨頭が触知できる。
1.× 肩峰骨折は、周囲の筋肉によって安定しているため、症状として、症状限局性圧痛、呼吸痛上腕の挙上、特に外転時に疼痛がみられる。著明な転位はない。
2.〇 正しい。肩甲骨頸部骨折は、肩関節烏口下脱臼と受傷時の外観が類似する。
なぜなら、両者とも上腕骨の近位骨片は軽度内転、遠位骨片は軽度外転を伴いやすいため。
3.× 鎖骨遠位端骨折は、骨折部の突出や圧痛が主な症状である。
4.× 上腕骨小結節骨折は、骨折部の局所的な圧痛や運動痛が主な症状である。
問題20 肩関節烏口下脱臼に対するヒポクラテス法で誤っているのはどれか。
1.足の外側縁を腋窩に当てる。
2.肩関節を内転、内旋で終える。
3.両手で上腕遠位部を把持する。
4.肩関節を外転外旋位に牽引する。
解答3
解説
1.〇 正しい。足の外側縁を腋窩に当てる。
2.〇 正しい。肩関節を内転、内旋で終える。
4.〇 正しい。肩関節を外転外旋位に牽引する。
【肩関節烏口下脱臼に対するヒポクラテス法】
患者を背臥位にし、術者は患側(脱臼した側)に座る。術者の足(外側縁)を患者の腋窩(肩甲骨の外側縁)に当て、これを支点に、患者の腕(通常は前腕や手首付近)を持ち、術者の足を支点にゆっくりと持続的に牽引を加える。牽引しながら、徐々に腕を外転・外旋させて、骨頭を関節窩の入り口に導くため肩関節を内転、内旋する。※腋窩部の神経・血管を損傷するリスクが指摘されており、現在では選択されにくくなっている。
3.× 必ずしも、両手で上腕遠位部を把持する必要はない。一般的に、両手で「前腕」遠位部を把持することが多いが、上腕骨の動きを正確に行う必要があるため、片手は前腕、片手は上腕で、肩関節の動きを誘導したほうが正確に行える。
 国試オタク
国試オタク